今日のおすすめ

専業主婦→復職→解雇…60社不採用から53歳で理想の仕事に転職
10年の専業主婦期間を経て、派遣社員として仕事復帰。突然の解雇や子どもの不登校に悩みながらも50代で異業種へ転職。「キャリアを諦めた」人生からの逆転劇!
もっと表示

40代からのキャリアとライフ

10年の専業主婦期間を経て、派遣社員として仕事復帰。突然の解雇や子どもの不登校に悩みながらも50代で異業種へ転職。「キャリアを諦めた」人生からの逆転劇!
もっと表示









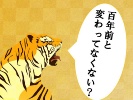



「人生の新たな扉を開けた挑戦者たち」に迫ります。一歩を踏み出す不安とどう向き合い、葛藤をどう乗り越えたのでしょうか。そして、彼女が扉を開けた理由はーー。


役立つ2本の特集と4つのARIAアカデミーをお届け!

「あの人にこれを聞きたい!」「あの人は今どうしてる?」――今、気になる人にインタビューをしました。

今、気になるニュースや知っておくべきテーマについて深掘りしてお届けします。
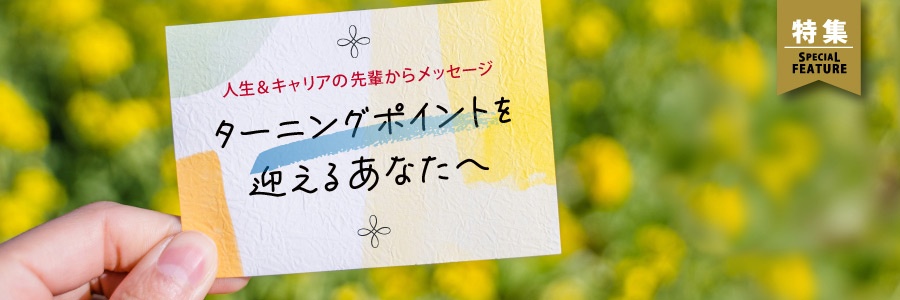
新年度を迎え、職場でもプライベートでも、新しい生活が始まるという人が多いのではないでしょうか。初めて管理職になった、思い切って資格への挑戦を決めた、といった前向きな変化に直面する人もいれば、役職定年を迎えた、病気が分かった、困った部下が異動してきた…など、不安を抱えている人もいるはず。人生の先輩たちから、「今、目の前にある壁」を乗り越えるメッセージをもらいます。